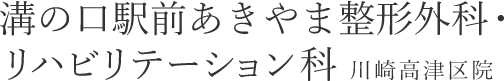電気療法とは
 筋肉に対して外側から電気で刺激を与えることで、筋力訓練や鎮痛を促します。人間の身体の細胞は、声帯電気といって微弱な電気を発生しながら命を維持しています。手足の曲げ伸ばしや内臓が機能するのも、声帯電気によって成り立っています。この声帯電気の性質をリハビリテーションで活用しているのが電気療法です。
筋肉に対して外側から電気で刺激を与えることで、筋力訓練や鎮痛を促します。人間の身体の細胞は、声帯電気といって微弱な電気を発生しながら命を維持しています。手足の曲げ伸ばしや内臓が機能するのも、声帯電気によって成り立っています。この声帯電気の性質をリハビリテーションで活用しているのが電気療法です。
筋力訓練に使用される
電気療法とは?
筋力訓練に対する電気療法には、神経筋電気刺激法「EMS」を用います。特に、神経障害や脳血管障害など、中枢神経麻痺にも使用されます。
EMS(神経筋電気刺激法)
「EMS」とは、「Electric Muscle Stimulation」の略です。筋力訓練を目的に、電気刺激を筋肉に与えます。
EMS(神経筋電気刺激法)
の効果
 EMSは、整形外科分野のほか、脳血管障害など中枢神経麻痺にも有効とされています。椎間板ヘルニアの場合、神経圧迫が原因で下垂足の状態になる可能性があります。下垂足とは、足首が上がらなくなって、つまずきやすい・脛が疲れやすい・足首の感覚が落ちるなどの症状が現れます。このような症状に対して、電気刺激を行うことで筋肉に構造学的に変化が起こり、改善されます。
EMSは、整形外科分野のほか、脳血管障害など中枢神経麻痺にも有効とされています。椎間板ヘルニアの場合、神経圧迫が原因で下垂足の状態になる可能性があります。下垂足とは、足首が上がらなくなって、つまずきやすい・脛が疲れやすい・足首の感覚が落ちるなどの症状が現れます。このような症状に対して、電気刺激を行うことで筋肉に構造学的に変化が起こり、改善されます。
当院の物理療法
現在のリハビリテーションのペースでは足りない方や、現在よりももっと早く筋力を上げたい方には、当院の物理療法をお勧めしております。お忙しい方には、物理療法のみの対応で筋力を上げることも可能です。
ご希望の方はどうぞお気軽にご相談ください。
物理療法の適応の疾患
変形性膝関節症
加齢や肥満などが原因で、膝関節の軟骨が擦り減ってしまい、炎症を起こした状態を変形性膝関節症と言います。歩いたり、走ったりする際の衝撃を吸収できなくなり、膝に痛みや腫れの症状が現れます。膝が痛くなることで、歩くことが苦痛になるため運動時間が大幅に減ってしまいます。徐々に脚の筋力が低下してしまい、膝への負担がさらに増える事態を招いてしまいます。変形性膝関節症による悪循環に陥る前に、物理療法などの治療を行うことで、痛みを軽減し筋力を維持することが非常に重要です。
四十肩・五十肩
(肩関節周囲炎)
四十肩・五十肩は一般的な名称ですが、医学的には「肩関節周囲炎」と言います。40歳から50歳頃に、突然肩が痛くなって腕が上に上がらなくなる状態になります。これは、肩の関節内の筋肉や腱が変性し、炎症するために起こる症状です。また、四十肩・五十肩は、血行不良や筋肉疲労などから来る肩こりとは異なる疾患です。自然治癒する場合もありますが、腕が上がらない・肩が痛い症状が長期的に続き、肩の可動域が狭いままとなることもあります。その場合は、適切な治療とリハビリテーションを行うことをお勧めしております。
腰部脊柱管狭窄症
脊柱管とは、椎骨が連なってできた神経が通る管を言います。この脊柱管が狭くなり、神経が圧迫される状態を脊柱管狭窄症と言います。脊柱管には、脳から続く脊髄神経があり、脳脊髄液で満たされています。
腰部脊柱管狭窄症では、腰部や臀部、脚などに痛みやしびれ、麻痺などの症状が現れます。脊柱管が元から狭い体質や、加齢に伴う変性が原因で発症します。そのうち、腰椎変性すべり症は腰椎がずれてしまう疾患で、腰部脊柱管狭窄症と大きく関連していると言われています。